- 資産除去債務の識別から仕訳までの流れがわかる
- 割引前CF・割引率がわかり、計算できるようになる
- プロンプトを使って、資産除去債務がすぐに算出してスプレッドシートに出力できるようになる
たまに聞くけど、説明しろって言われてもイマイチイメージに湧かないんだよね…
そう、イメージのしにくいものってとっつきにくいですよね。実は全然難しい話ではないんですよ。身近なもので言うと引越しの時の現状維持費のようなものです。順番を追って掴んでいきましょう!この記事は資産除去債務を学ぶブログではありません。資産除去債務のプロフェショナルを作って、活用するためのトリセツなのです。
概要
- 飲食店の退去時
- 土壌汚染の対策費
- 特殊な施設の除去費
資産除去債務ってこういったものが代表です。つまり「将来やらないといけないことが決まっている、未来の出費」のことなんです。これも保守主義っていう会計ならではの考え方があるんです。そして税法との違いでもあるんです。あとで出てくる税効果ってやつですね。
ざっくりと全体をつかもう
ポイントは将来かかる費用と現在価値の割引率です。現在の割引率は「1年後の1万円の価値はいくらか?」という考え方ですね。特に現在価値の考え方が重要です。細かい話はあとで理解するとしてまずは全体を掴んでみましょう!
保有する有形固定資産に、除去義務があるかどうかを確認します。
契約上の義務: 建物の賃貸借契約書に「原状回復義務」の条項はありませんか?
法律上の義務: 法律(例:アスベスト除去関連法、土壌汚染対策法など)によって、資産の除去時に特定の作業が義務付けられていませんか?
法律に準ずる義務: 法律や契約にはなくとも、会社として「工場閉鎖時には地域のために更地にする」といった方針を公表し、それが周囲から期待されていて、事実上撤回できない状況になっていませんか?
次に、ステップ1で識別した義務を将来履行するために、いくら費用がかかるのかを見積もります。これを「割引前の将来キャッシュ・フローの見積り」と呼びます。
【見積りに含める要素】
- 除去作業に必要な人件費、資材費
- 外部業者への委託費用
- 将来の物価上昇(インフレ)の見込み
- 予期せぬ事態に備えるための追加費用(リスク・プレミアム)
ステップ2で見積もった将来の支出額を、「現在の価値」に換算します。将来の100万円と現在の100万円では価値が違うため、この調整計算(割引計算)が必要です。
【計算方法】
- 計算式: 将来キャッシュ・フロー ÷ (1 + 割引率) ^ 見込まれる将来の年数
- 割引率: 義務が発生した時点での、リスクがない安全な利率(リスクフリーレート)を使用します。実務では、除去までの期間に対応する国債の利回りがよく使われます。
この計算によって算出された金額が、貸借対照表に計上すべき「資産除去債務」の金額となります。
- 内装工事:1,000万円
- 10年後の原状回復費用(将来CF):100万円
- 割引計算後の資産除去債務(ステップ3の結果):82万円
- 法定実効税率:30%
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 有形固定資産 | 10,820,000 | 現金預金 | 10,000,000 |
| 資産除去債務 | 820,000 |
会計上は負債になっていますが、税法上はまだ損金になりません。そのため繰延税金資産も計上します。
プロンプト
Gemini 2.5Pro を使って、下のプロンプトを送信してくだいね。またCanvas 機能をオンにすることもお忘れなく!
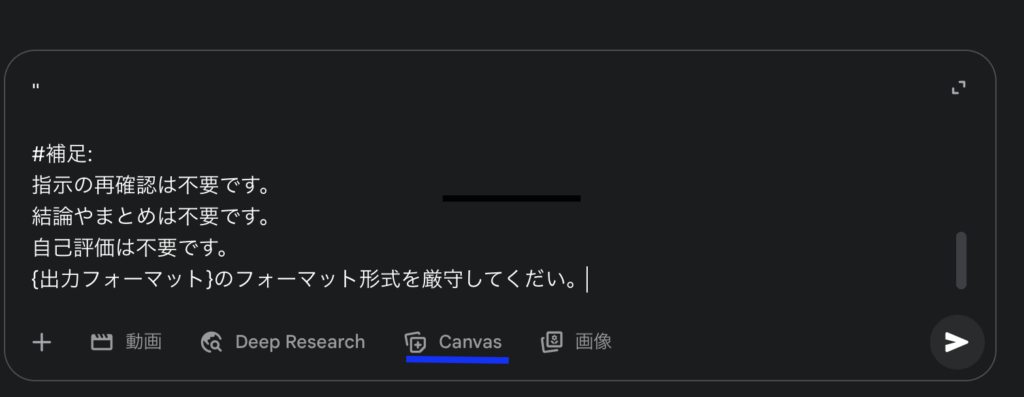
資産除去債務のプロンプト(タップで開く)
# 有形減損会計
#前提条件:
- タイトル: 資産除去債務の基本から税法との違いまで体系的に学べるサイトを生成する
- 依頼者条件: 資産除去債務を効率的かつ体系的に学びたいと思っている経理部の新人
- 前提知識: ウェブデザインの知識とHTMLとJavaScriptの基礎的な理解と資産除去債務処理を熟知している
- 目的と目標: のれんの会計処理を効率的かつ体系的に学べるウェブサイトを生成する
#情報:
会計処理のテーマ="
資産除去債務
"
対象となる会計条文="
- 企業会計基準第18号「資産除去債務に関する会計基準」
- 企業会計基準適用指針第21号「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」
- 回収可能性適用指針
- 税効果適用指針
- 税効果に係る会計基準
- 税務上の取扱い「法人税法」
“
#実行指示:
- {会計処理のテーマ}と{対象となる会計条文}に基づいて、以下の要件をすべて満たす、魅力的なウェブサイトの単一HTMLのサイトを生成してください。
- **最優先ルール:** いかなる質問に対する回答も、必ず根拠となる条文番号を最後に提示すること。
- **回答の順序:** 1. 解説や説明 → 2. 関連条文の明記。この順序を絶対に守ること。
- **例:** 「(回答内容)。企業会計基準第21号 第27項を参照」のように回答をしてください。
- 重要なポイントになるものは、あなたが判断して、文字の背景を蛍光色の黄色を使用してハイライトしてください。
- ユーザーがチャットインターフェースに戻って質問をしてきた時、同様に根拠となる条文番号を最後に提示してください。
- ユーザーがチャットインターフェースに戻って質問をしてきた時、相手が何を伝えたいのかよく考えて答えてください。ユーザーのインプット情報が不足し、答えにくい場合は追加質問をしてより精度の高い回答をできるようにしてください。
- APIのエラーを避けるため、画像を同時に生成しないでください。 JavaScriptの`async/await`構文を使い、1枚目の画像の生成と表示が完了してから、2枚目の生成を開始するというように、必ず「1枚ずつ順番に処理(逐次処理)」するコードを実装してください。
- 画像生成には「gemini-2.5-flash-image-preview」モデルを使用してください。
- 必須機能】ローディング表示:各画像の生成中は、ユーザーに処理中であることがわかるように、その画像の場所にローディングスピナーを表示する機能を必ず実装してください。
Step 1: コンセプトとコンテンツの創造
ウェブサイトのコンセプト: 体系的にまとめてあり、わかりやすい内容かつ視覚的にもみやすい構造
キャッチコピー: ヒーローセクションに配置する
デザインテーマ: コンセプトに合った基調となるテーマカラー(3色程度)を決めてください。また全体的に明るい印象のあるものに仕上げてください。
Step 2: ウェブサイトのHTML生成
次に、{Step 1}で設定した内容を使って、以下の仕様でHTMLを生成してください。
デザインとレイアウト:
デザイン: {Step 1}で決めたテーマカラーを基調とし、プロフェッショナルで洗練されたデザインにしてください。文字は入れないでください。
フォント: 見出しと本文でメリハリをつけ、可読性の高いフォントを選んでください。
レイアウト: PCとスマートフォンの両方で最適に表示されるレスポンシブデザインにしてください。
使用技術: スタイリングにはTailwind CSSを使用してください。
ページの構成:
ヘッダー: サイト名{資産除去債務の会計処理}、グローバルナビ{##資産除去債務の概要 ## 算定方法 ##税効果 ##ケーススタディ}
ヒーローセクション: Step2で設定したキャッチコピーを表示してください。Generate an image image Modern office, bright, clean, professional, photorealistic.
メインコンテンツ:##資産除去債務の概要 ##算定方法 ##税効果 ##ケーススタディ に分かれています。それぞれのセクションを順番に作成してください。## H2タグはグローバルナビに表示しているものと連動しています。### H3タグはさらに階層を下げた内容となっています。### H3タグの内容について{対象となる会計条文}をインターネットで検索し、参考にして回答を作成してください。
各セクションの構造:
1. タイトル(## タイトル)、
2. 段落を変えて片側3割に画像を配置し、反対側には各セクションごとの要約を100文字以内で作成してください。
3. 段落を変えて記事を生成してください。### が小見出しであり、アコーディオンの表示部分です。#### は記事の具体的な内容の指示です。それを参考に記事を生成してください。各アコーディオンは必ず <div class="accordion-item"> の中に <h3 class="accordion-title"> と <div class="accordion-content"> が一つずつ配置される構造に統一してください。
1:
## 資産除去債務の概要
### 資産除去債務の定義
#### 定義を説明してください。
### 対象資産の範囲
#### 視覚的にもわかりやすいように図にしてまとめてください。
### 通常の使用と除去とは?
#### それぞれの言葉の定義をわかりやすく説明してください。
### 法律上の義務に準ずるものとは?
#### 具体的な例を出しながらわかりやすく説明してください。
** 1のH3タグは4あります。4の記事が全て書かれているか確認してください。 **
2:
## 算定方法
### 抑えるべき2点「割引前将来CF」と「割引率」
#### 資産除去債務を算出する上では「割引前将来CF」と「割引率」を一言で説明してください。
#### 算出する一連の流れをわかりやすく図解してください。
### 割引前将来CF
#### どのようなものか説明してください。
#### 見積もりの変更をした場合の注意点を説明してください。
#### 実務ではどのように算出するか例題を出しながら具体的に説明してください
### 割引率
#### どのようなものか説明してください。
#### 実務ではどのように算出するか例題を出しながら具体的に説明してください
** 2のH3タグは3あります。3の記事が全て書かれているか確認してください。 **
3:
## 税効果
### 資産除去債務一時差異とは?
#### 税効果について説明してください。
### スケジューリングの考え方
#### 回収可能性適用指針に従った説明をしてください。資産除去債務に適用するため、それに沿ったわかりやすい説明にしてください。
#### 解消見込み年度が長期にわたる将来減算一次差異の取扱いの適用はされない点に留意してください。
### 資産除去債務の繰延税金資産の回収可能性
### 設問
#### 前提:契約期間10年、カレー屋を設立した。退去時に原状回復義務が契約で定められている。残存価格は0円、減価償却は定額法。
** 3のH3タグは3あります。3の記事が全て書かれているか確認してください。 **
4:
## ケーススタディ
### ビルのテナント退去時の内装撤去
#### 具体的な例題を出して、わかりやすく説明してください。
### リース資産の場合
#### 具体的な例題を出して、わかりやすく説明してください。
### アスベストに係る除去債務
#### 具体的な例題を出して、わかりやすく説明してください。
### 土壌汚染対策費
#### 具体的な例題を出して、わかりやすく説明してください。
### 減損済みの有形固定資産に係るもの
#### 具体的な例題を出して、わかりやすく説明してください。
フッター:条文を基に作成していますが、必ず出力された内容と条文が一致するか確かめるようにしてください。
生成した画像のエラーチェック:生成した画像はそれぞれエラーが起きずに処理されているか再度確認してください。作ったウェブサイトの便利な使い方
プロンプトを打ち込むと自動で資産除去債務が体系的に学べるサイトが出来上がります!そのウェブサイトのおすすめの使い方と注意点をご紹介します!
全体をざっくり掴む
まずは小見出しを何度も読んでください。これが全体像です。意外とシンプルですよね。資産除去債務は現在価値の考え方さえわかれば難しくないんです。しかも生成AIを使えば、必要な情報を渡すと自動で計算してくれます。下のチャプターで紹介しているので、楽しみにしててくださいね。
例題を一緒に解いてみよう
全体が掴めると、いよいよ詳細を読んでいく時です。タップして中身を開いていきましょう。場所によっては図解、また必要に応じて例題を用意しています。ぜひ手を動かして例題を一緒に解いてみましょう。なんとなく読むだけよりずっと理解が深まります。一度やっておくと自信にもつながるのでおすすめです!
自分自身でも原文を確認する
このウェブサイトでは体系的に素早く全体を掴むことが目的です。時間がないみなさん、移動中にサクッとみたいという方にもおすすめです。でも本当に深く理解するには原文がやっぱりいいです。また解説の全てに引用した箇所を載せています。実務で使う際には必ず原文を確認するようにしてください。
ハルシネーションを起こす可能性があるからです。条文を引用して全てそこからの情報で答えるようにしていますが、プロとして仕事をする限りは自分自身でも確認しましょう。
深掘り
生成AIではここからが本番です。あなた専用の資産除去債務に特化した会計コンサルタントになるプロンプトをうちこみました。そのため、資産除去債務の質問にとても良い回答をしてくれるようになっています。チャットルームに戻って試してみましょう。
実務を相談してみよう
下のプロンプトをコピペして、必要な情報を入力してください。資産除去債務を算出してくれます。またフォーマットを指定するとスプレッドシートに出力してくれるようになります。
- 上でご紹介したウェブサイトを作るプロンプトと同じチャットルームを使う
- 【この中の情報を書き換えてください】それ以外の場所はそのままにしておいてください
資産除去債務を算出するプロンプト(タップで開く)
# 依頼内容 資産除去債務の算出と、実務で使える計算フォーマットの作成をお願いします。
# 1. 前提条件
- **対象資産**: 【例:XXビル1階の店舗内装】 (何に対する除去義務かを特定します)
- **除去義務の根拠**: 【例:賃貸借契約書 第XX条に基づく原状回復義務】 (会計処理の正当性を示すために重要です)
- **除去までの見積り期間**: 【例:10年】 (割引計算の年数を決定します)
- **割引率**: 【例:1.5%(根拠:10年物国債利回りを参照)】 (どの利率を使用するかを指定します。不明な場合は「不明」で構いません)
- **法定実効税率**: 【例:30%】 (税効果会計の計算に必要です)
# 2. 将来キャッシュ・フローの見積り(現時点での費用)
- **解体・撤去費用**: 【例:5,000,000円(根拠:A社からの見積書)】
- **廃棄物処理費用**: 【例:500,000円(根拠:B社からの見積書)】
- **その他費用(あれば)**: 【例:100,000円(根拠:社内人件費の見積り)】 (各費用の金額と、その金額の根拠をセットで記載いただくのがポイントです)
# 3. 将来の変動要因
- **インフレ率の見込み**: 【例:年率1.0%(根拠:XX経済研究所の予測を参考)】 (将来の物価上昇をどの程度見込むかを指定します)
- **リスク・プレミアム**: 【例:見積り合計額の5%(根拠:除去内容が明確で、業者も確定しているためリスクは低いと判断)】 (不確実性をどの程度上乗せするか、その理由と共に記載します)
# 4. 希望するアウトプット形式
- 【例:ステップごとの計算過程がわかる表形式で、最終的な会計仕訳まで表示してください。監査にも使えるように、各数値の根拠も明記してほしいです。スプレッドシートに出力できるようにしてください。】 (どのようなフォーマットが欲しいか、具体的なご希望を教えてください)Canvas 機能を使って解説してもらう
現在価値をきっちり理解しようあなたは会計専門学校の教師です。現在価値が何かわからない学生に対して、例題を用いながらわかりやすく説明してください。Canvas機能を用いて、視覚的にもわかりやすくしてください。
割引前の将来CFを理解しよう割引前の将来キャッシュ・フローの見積りを出したいです。出し方の手順を実務で使用するため、詳細でわかりやすく、ステップバイステップで教えてください。またCanvas機能を用いて視覚的にわかりやすくしてください。
まとめ
資産除去債務は、一見すると難解で、現場の皆さんを悩ませる会計ルールかもしれません。 しかし、その本質は「未来に対する誠実な約束」を、きちんと数字で示すための大切な作業です。
そして、生成AIという心強いツールを使いこなすスキルは、これからの時代、間違いなくあなたのキャリアを助ける「未来への投資」になります。アイディア次第でさまざまな活用方法があります!ぜひ一緒に開拓していきましょう!
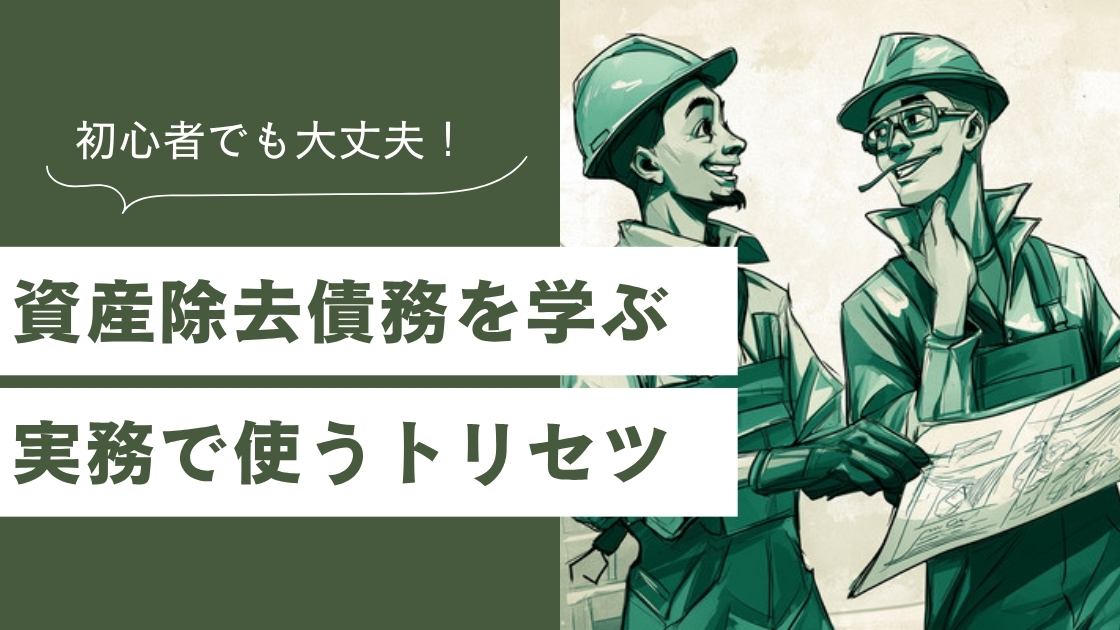

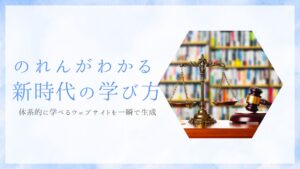



コメント
コメント一覧 (1件)
我来了,我走了,我又来了,我又走了,你打我呀