- 一次情報である会計基準書が大切である
- のれんを体系的に学べるウェブサイトを自動で作成できる(無料プロンプト)
- 作成したウェブサイトの活用方法
M&Aで成長を加速させる会社が増えてきましたね。そこでとても大切な論点となるのがのれんです。複雑な処理を経て計上しますが、学習しても実践で応用することってとても難しいですよね。今回はのれんの基礎から税法との違いまで体系的に学べるウェブサイトを作成して、自社事例で質問して時に専門家のような返答をさせる生成AIを作ります。ウェブサイトを作るといっても、私が作成したプロンプトを使えば自動で作成できるのでご安心を!
のれんの会計処理って難しいって聞くけど、一度体系的にじっくり学んでみたいなあ
勉強はしたけど、実務で特殊なケースの場合はどう処理すればいいか自信がない…
実はのれんってとても難しくて、金額的にも大きくなりがちなのでとてもデリケートな論点の一つなのです。先ほどのような悩みを持っていることは当然のことなのかもしれませんね。そんなあなたに朗報です! この記事では、最新の生成AIを活用して、あなただけののれん専門アドバイザーを手に入れる画期的な方法をご紹介します。
これから紹介するプロンプトを使えば、のれんの会計処理を体系的に学べるウェブサイトが瞬時に完成します。しかも、そのAIはあなたの個人的な質問にも答えてくれる、まさに強力なパートナーになってくれるのです 。
- 子会社を取得したけれど、のれんの金額をどう計算する?
- のれんの償却が必要なケースってあるの?
- 減損テストって、具体的にどうやるの?
このようなこともスッキリわかるようになりますよ。
提案する新しい「学び方」
まず、この記事を取扱説明書のようなイメージで捉えてみてください 。大切なのは、ただ読むだけでなく、実際に生成AIを使って、どんな答えが返ってくるのかをご自身で確かめてみることです。自分で手を動かしてAIと対話することで、その癖やコツが掴め、あなたの業務に本当に役立つスキルが身についていきます。
なぜプロは「会計基準」という一次情報にこだわるのか?
少しだけ、専門的な話をさせてください。会計処理を学ぶ上で、一次情報にこだわることは非常に重要です。なぜなら、それが最も信頼性が高い情報だからです 。では、会計における一次情報とは何でしょうか? それは、企業会計基準委員会等が公表している「会計基準」や「適用指針」といった公式ルールブックです。私も会計のプロとして、会計処理について判断に迷ったときは、必ずこの会計基準の原文にあたります 。実はこの会計基準、インターネットで検索すれば誰でも無料で見ることができるのです。
- 会計基準書や適用指針のような会計条文を使うことが大切
難解な会計基準もAIがあなた専用の”翻訳家”
とはいっても、会計基準の文章は難しそう…
基準書なんてたくさんあるからそれで足りてるかもわからないよ
そんな声が聞こえてきそうですね。確かに、会計基準は独特の言い回しが多く、慣れていないと解釈が難しい部分もあります 。探している内容が、適用指針やFAQ、場合によっては税法の条文に書かれていることもあり、慣れないうちはとても時間がかかって大変…
でもご安心を! 今回のウェブサイトは、会計基準の条文に沿いながらも、非常に分かりやすい言葉で解説をしてくれます。まずはAIが生成したウェブサイトの説明文を読んで、全体像を掴んでください。必要に応じて図解や設例も交えて解説してくれるので、複雑な内容もイメージしやすくなっています。
その解説の根拠となった会計基準の条文も示してくれます。 同僚に質問されたとき、「それは会計基準第◯号の◯項にこう書かれていますよ」と根拠を示して答えられたらちょっとカッコよくないですか!?
【実践】あなただけの「のれん解説サイト」を生成しよう
お待たせしました!
それでは、実際にウェブサイトを生成してみましょう。 今回は、Googleの生成AIであるGeminiを使います。
以下のプロンプト(指示文)をコピーして、Gemini Pro 2.5のチャット画面に貼り付けて送信してください。
またCanvas 機能もオンにすることを忘れないように気をつけてくださいね。
プロンプトを打ち込もう
プロンプト
# のれんの会計処理
#前提条件:
- タイトル: 連結会計処理の中で、のれんについて基礎から応用まで学べるチャットルームを生成する
- 依頼者条件: のれんの会計処理を効率的かつ体系的に学びたいと思っている経理部の新人
- 前提知識: ウェブデザインの知識とHTMLとJavaScriptの基礎的な理解とのれんの会計処理
- 目的と目標: のれんの会計処理を効率的かつ体系的に学べるウェブサイトを生成する
#情報:
会計処理のテーマ="
のれんの会計処理
"
対象となる会計条文="
- 企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」:
- 企業会計基準適用指針第10号「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」:
- 企業会計基準第17号「事業分離等に関する会計基準」:
- 企業会計基準第7号「資産除去債務に関する会計基準」
- 企業会計基準適用指針第31号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」
- 企業会計基準適用指針第6号_固定資産の減損に係る会計基準の適用指針
- 企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」
- 税務上の取扱い「法人税法」
- IFRS第3号「企業結合」
“
#実行指示:
- {会計処理のテーマ}と{対象となる会計条文}に基づいて、以下の要件をすべて満たす、魅力的なウェブサイトの単一HTMLのサイトを生成してください。
- **最優先ルール:** いかなる質問に対する回答も、必ず根拠となる条文番号を最後に提示すること。
- **回答の順序:** 1. 解説や説明 → 2. 関連条文の明記。この順序を絶対に守ること。
- **例:** 「(回答内容)。企業会計基準第21号 第27項を参照」のように会話をしてください。
- ユーザーがチャットインターフェースに戻って質問をしてきた時、同様に根拠となる条文番号を最後に提示してください。
- ユーザーがチャットインターフェースに戻って質問をしてきた時、相手が何を伝えたいのかよく考えて答えてください。ユーザーのインプット情報が不足し、答えにくい場合は追加質問をしてより精度の高い回答をできるようにしてください。
Step 1: コンセプトとコンテンツの創造
ウェブサイトのコンセプト: 体系的にまとめてあり、わかりやすい内容かつ視覚的にもみやすい構造
キャッチコピー: ヒーローセクションに配置する、「のれんを体系的に素早く知る。」
デザインテーマ: コンセプトに合った基調となるテーマカラー(3色程度)を決めてください。また全体的に明るい印象のあるものに仕上げてください。
会計処理のテーマ:のれん
Step 2: ウェブサイトのHTML生成
次に、{Step 1}で設定した内容を使って、以下の仕様でHTMLを生成してください。
デザインとレイアウト:
デザイン: {Step 1}で決めたテーマカラーを基調とし、プロフェッショナルで洗練されたデザインにしてください。文字は入れないでください。
フォント: 見出しと本文でメリハリをつけ、可読性の高いフォントを選んでください。
レイアウト: PCとスマートフォンの両方で最適に表示されるレスポンシブデザインにしてください。
使用技術: スタイリングにはTailwind CSSを使用してください。
ページの構成:
ヘッダー: サイト名{のれんの会計処理}、グローバルナビ{##概念と基礎 ##基本的会計処理 ##減損処理 ##税務上ののれん}
ヒーローセクション: Step2で設定したキャッチコピーを表示してください。背景は単色で、ウェブサイトのイメージが明るくなることを意識してください。
メインコンテンツ:##概念と基礎 ##基本的会計処理 ##減損処理 ##税務上ののれんに分かれています。それぞれのセクションを順番に作成してください。## H2タグはグローバルナビに表示しているものと連動しています。### H3タグはさらに階層を下げた内容となっています。### H3タグの内容について{対象となる会計条文}をインターネットで検索し、参考にして回答を作成してください。
1:
## 概念と基礎
### のれんとは一体なに?
### 超過収益力
### 取得時の処理方法
#### 取得原価の分配
#### BSに計上されるのれん
### 取得後ののれんの概念
#### 償却方法
#### 減損テスト
** 1のH3タグは4つあります。4つの記事が全て書かれているか確認してください。 **
2:
## 基本的会計処理
### のれんが発生する取引の種類と処理方法
#### 取得に該当した場合
#### 共通支配下の取引の場合
### 代表的な取引の形式(以下のH4タグをチャート式に表示して視覚的にわかりやすく解説してください。)
#### 個別
#### 連結
#### 逆取得
### みなし取得日とは?(設例を通して説明してください。)
### 取得時の関連費用の処理方法
#### 個別財務諸表
#### 連結財務諸表
#### 決算期をまたいだ場合
### 条件付取得対価の処理
#### 条件付取得対価とはどういう取引?(設例を通して説明してください。)
### 取得原価の認識
#### 分配の注意点(勘定科目ごとに分けて、評価方法を説明してください。また見やすいように、図で表示してください。)
#### 識別可能資産と負産とは?
#### 識別可能資産と負債の分配額の算定方法(観察可能な市場の有無で処理方法が違います。それぞれを説明してください。また簡便的な処理方法についても解説してください。)
### 分配が完了していない時の暫定的な会計処理方法
#### 基本的な処理方法(完了していないときは暫定処理をする。期限は1年以内。のれん償却額は遡及して認識。)
#### 対象となる勘定科目(算定が困難な勘定科目のみが対象)
### 暫定的な処理ののれんが確定した時は?
#### 基本的な処理
#### 翌期に確定した時の表示方法
#### のれんの償却方法
### のれんの償却方法は?
#### のれん償却の会計処理方法(開始時期、またみなし取得時について解説してください。)
#### 重要性がない場合の処理方法
#### 償却費用の表示箇所(償却額:販管費、重要性が低い場合:販管費、減損損失:特別損失)
### のれんの償却期間の決め方は?
#### 投資回収期間に基づくアプローチ
#### 事業計画・製品ライフサイクルに基づくアプローチ
#### 関連する無形資産の対応年数に基づくアプローチ
#### 被取得企業が既存の事業を行うと見積もられている期間
### 複数の資産グループを取得した場合ののれんの取扱は?
### 負ののれんの会計処理
#### 負ののれんとは?
#### 開示方法
#### 発生した利益の計上方法
** 2のH3タグは12あります。12の記事が全て書かれているか確認してください。 **
3:
## 減損処理
### 減損判定の概要
### 減損判定の流れ(主な流れをチャートを使って説明してください。企業会計基準適用指針第6号に従って行います。)
### 負ののれんを負債の部へ計上している時
### 減損の兆候とは?(下に主な減損の兆候を挙げました。他にもよくあるものを挙げて、説明をしてください。)
### 減損の兆候の具体的な例(減損適用指針17項に従って処理する)
#### 営業損失やマイナスのキャッシュフロー
#### 経営環境の悪化(市場環境の悪化、技術的環境の悪化、法律的環境の悪化など)
#### 事業の再編や処分計画(当初の計画から大きな乖離が生じたなど)
### 減損兆候の認識の流れ
#### 資産グループに分ける
#### その他減損適用指針52項に従って検討する
### 減損損失の測定方法は?
### 将来キャッシュフローの見積もり期間
### 子会社の減損処理の要否
### 減損損失の非支配株主持分への分配
### 売却時に売却損が見込まれる際の減損判定方法
### 連結子会社と持分法適用会社との減損の相違点
#### 持分法適用会社ののれんの減損の兆候
** 1のH3タグは12あります。12の記事が全て書かれているか確認してください。 **
4:
## 税務上ののれん
### 税務上ののれんとは?
### 資産調整勘定等が生じる場合
### 資産調整勘定、差額負債調整感情の算定方法
### 資産調整勘定及び差額負債調整勘定の減額
### 会計上ののれんと税務上ののれんの違い
### 組織再編税制とは?
### 資産調整勘定に対する税効果会計
** 4のH3タグは7あります。7の記事が全て書かれているか確認してください。 **
フッター:条文を基に作成していますが、必ず出力された内容と条文が一致するか確かめるようにしてください。
* メインコンテンツで設定したH3タグを全て表示してください。またこのタグではアコーディオンを使用し、それを開くとH4タグの説明を見ることができます。またアコーディオンを使用することで、スペースを無駄にすることなくユーザーが情報を見つけやすくするとができます。表示する部分はH3タグの部分のみ表示してください。H4タグを表示すると視覚的に悪くなるため、気をつけてください。
H3タグ内:Step1で詳細をH4タグで書き出しています。それを{対象となる会計条文}から情報を探して、記事にしてください。自信がない場合は明確にその旨を伝えてください。また見出しの先にはアイコンを設定し、視覚的にも楽しい雰囲気を出してください。生成した文章は固くならず、親しみやすい文章にしてください。また状況に合わせて、例えを出しながらイメージしやすくしてください。引用した条文元を表記してください。
対象となる会計条文:{対象となる会計条文}をインターネットで検索し、最新のものを探してください。答える内容な各会計条文内から答えてください。また答えた際には必ず引用元を提示してください。また本文とは区別するため、改行し、一番下の行に記載してください。(例:企業会計基準第21号27項)
** メインコンテンツの内容の網羅性が非常に大切です。1:概念と基礎には3のH3タグ、2:基本的会計処理には12のH3タグ、3:減損処理には12のH3タグ、4:税務上ののれんには7のH3タグがあります。このH3タグの数と同数のアコーディオンになっているコンテンツを作成してください。完成したサイトを120%活用する3つのコツ
ウェブサイトが完成したら、ぜひ以下の方法で活用してみてください。
1. まずは上から順番に読んでみよう
このウェブサイトはのれんを初めて学ぶ方でも体系的に知識を習得できるよう、上から順番に読んでいく構成になっています。まずは全体に目を通し、のれんの全体像を掴んでみましょう。書籍でいう小見出しが並んでいるので、そこを読んで全体を把握すると頭に入りやすいですよ。
2. スマホとPCで使い分けよう
このサイトは、PCでもスマートフォンでも見やすいように自動でデザインが最適化されます。通勤中にスマホでインプットし、職場のPCで実際の業務に活かす、といった使い方も便利です。
3. AIに直接質問してみよう!
ここからが本番です。ウェブサイトを一度閉じ、チャット画面に戻って、作成したAIに直接のれんに関する質問を投げかけてみてください。
「うちの会社ではこういうケースなんだけど、どう処理すればいい?」
「償却は不要って言われたけど、本当にそう?」
といった、あなた自身の実務的な疑問を直接聞いてみましょう。
しかも今回のAIは足りない情報を聞き返してくれるように設定しています!
なので対話を重ねるほど理解が深まります!
まさに、無料で使える優秀な会計コンサルタントですね。
ファクトチェックは必ずしよう
条文をもとに回答するようにしています。しかしそれでもハルシネーションは起きます。必ずあなた自身でファクトチェックする癖はつけてくださいね。参照先を書き出してくれるため、会計条文を確認しにいくことは簡単です。
まとめ
「のれんって、なんとなく苦手…」
そんな気持ちから抜け出したいと思ったら、まずはこの方法を試してみてください。今は予算も人手も足りない…そんな企業でも、AIを活用すれば知識も質も諦めなくて済む。私は心からそう信じています。
さあ、あなた専用の「のれん先生」を作ってみましょう!
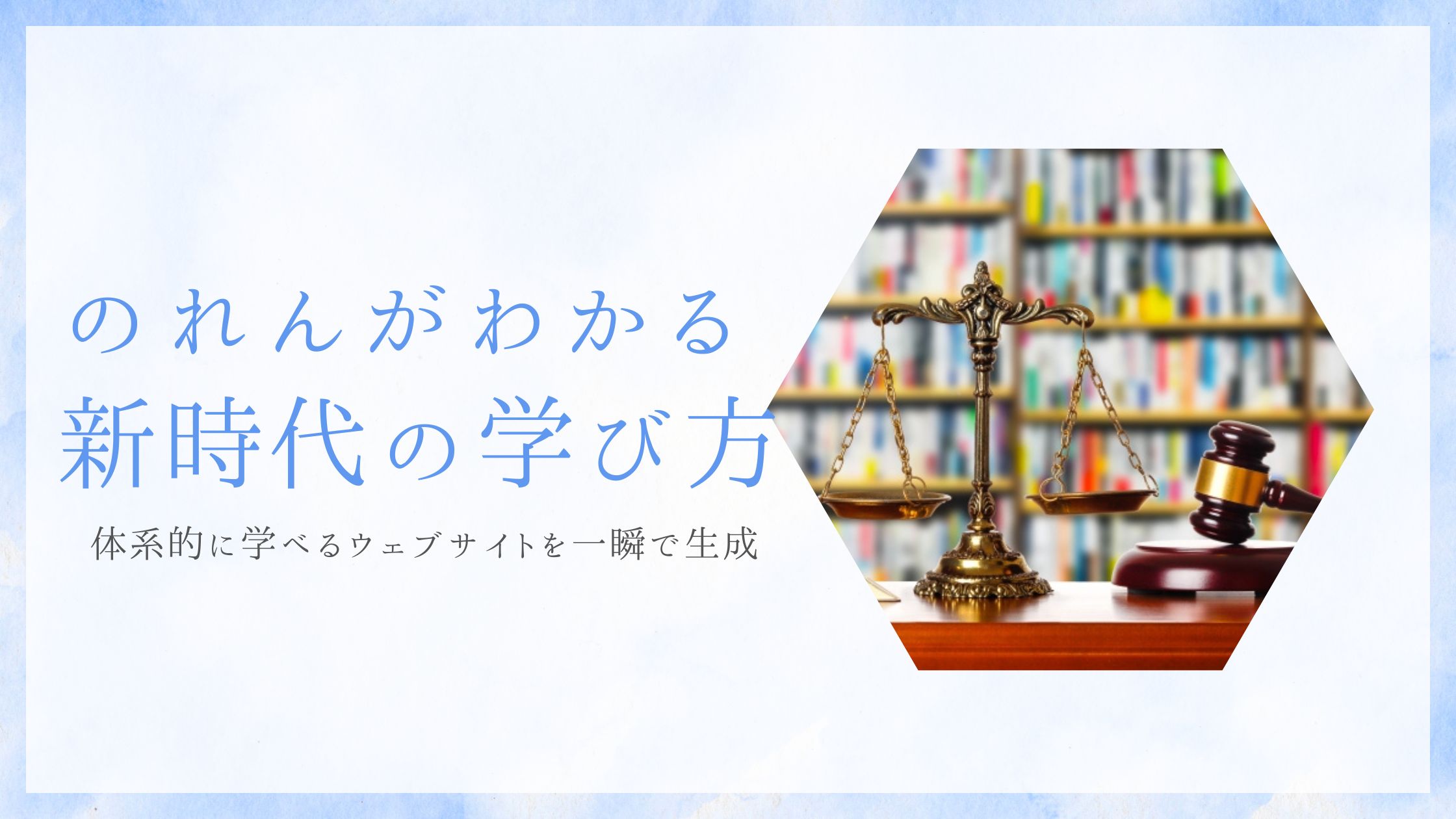


コメント