- 貸借対照表は企業の持ち物リスト
- 有価証券報告書を分析してくれるプロンプト
- 押さえるべき基本的な財務指標
- さらに深く分析する質問集
この記事を読んだ後、あなたは会社が発表している有価証券報告書を使って、その会社の財務分析ができるようになっています。
今回は財務三表と言われている①貸借対照表、②損益計算書、③キャッシュフロー計算書の中の「①貸借対照表」に焦点を当てています。
株式投資をしたいけど、どうやって企業のことを調べたらいいかわからないよ…
貸借対照表は知ってるけど、どういうところがポイントなのかよくわからん!
生成AIの財務分析って本当に使えるの?
いざ企業研究をしようとしても、財務分析ってどうやったらいいのか意外とわからないんですよね。どういった指標が役に立つのかもイマイチわからないし、そもそも計算もめんどくさいし、、、
とまあ、やらない理由を探すとキリがないので早々と進めていきましょう。
まず今回の分析で必要なものが調べたい企業の有価証券報告書です。これは金融庁のウェブサイトであるEDINETから無償でダウンロード可能です。
企業分析をするときは最も信頼度の高い一次情報から得るようにしましょう。会計監査人という会計のプロがチェックしたお墨付きの情報源、しかも無料なので絶対に活用したいですね!
貸借対照表とは「持ち物リスト」
貸借対照表は簡単にいうと持ち物リストです。
- 普通預金 100
- 持ち家 1000
- 住宅ローン 600
- 正味の財産 500
その中の数字を分析していくと、企業の強みや弱みがどんどん見えてきます。それはまるで人間の健康診断のようで、数値の変化や異常値から、企業の体調不良を早期発見できるのです。
監査で資金繰りに困っている企業を見ると、必ず貸借対照表に兆候が現れています。流動比率が100%を下回る企業、現金・預金が前年比で大幅減少している企業、売掛金の回転期間が業界平均1.88月を大幅に超える企業…。これらの兆候を早めに見つけておけば先に大きな一手を打つこともできます。
このように分析することで、単純な「持ち物リスト」という貸借対照表の見方から「健康診断書」という分析ツールとして活用できます。
数値分析方法も下で紹介しているので楽しみにしててくださいね。
コピペだけ!貸借対照表を分析するプロンプト
分析したい企業の3期分の有価証券報告書のPDFをEDINETからダウンロードしてください。そして生成AIにそのPDFを読み込ませてください。そして以下のプロンプトを打つと自動的に対象企業の分析を行なってくれます。
生成AIはChatGPTだとo3以上、GeminiだとPro2.5を推奨いたします。Claudeだと有価証券報告書は読みきれないことが多いです。(おすすめはGemini Pro2.5です)
貸借対照表分析プロンプト(タップで表示)
#前提条件
– タイトル:貸借対照表分析プロンプト
– 依頼者条件:企業の財務分析に関心があるが、どのように財務諸表を読めばいいかわからない株式投資家初心者。
– 制作者条件:財務諸表の読み解きと分析に長けたファイナンシャルアナリスト。
– 目的と目標:3期分の有価証券報告書の貸借対照表を用いて企業の財務状況を分析し、健全性やリスクを評価する。
#実行指示
添付ファイルの3期分の有価証券報告書を基に、詳細な貸借対照表分析を行ってください。
各期の主要項目を比較し、3期分の財務状態の変化を定量的に評価してください。
基本的な財務指標を算出し、比較してください。
{出力フォーマット}を参考にして出力してください。
参考フォーマット =”
企業名:{企業名}
分析対象期間:{分析対象期間}
貸借対照表の分析結果の要約:
財務指標:{自己資本比率、流動比率、ROE、売上高層利益率、総資産回転率、財務レバレッジ}3期を並べて比較できるようにしてください。スプレッドシートに出力できるようにしてください。それぞれの財務指標をもとに分析結果の所感を述べてください。
業界比較:インターネットを使って、分析した対象企業の業界のことを調べてください。そして、業界の基本的な傾向、最近の流れを加味し対象会社の分析をしてください。分析結果をレポートでまとめて、この欄で出力してください。レポート結果は良い言葉だけを並べるのではなく、批判的な視点も大切にしてください。ただし、無理に批判をする必要はなく、最も大切なことは第三者として冷静な分析結果を伝えることとしてください。
“
#補足:
指示の再確認は不要です。
結論やまとめは不要です。
自己評価は不要です。
{出力フォーマット}のフォーマット形式を厳守してくだい。
出力された基本的な内容を押さえておこう
すごい文章量の返事が返ってきちゃった!!
よくわからないことをたくさん言われるから億劫になるんよね
いきなりたくさんの文字がツラツラと返ってきてくると読むのも疲れちゃいますよね。でもご安心を!落ち着いて読んでいくとそれほど難しいことではないのです。
基本的な指標
まず、基本的な財務指標をご紹介しますね。
- 自己資本比率:(自己資本 ÷ 総資本 × 100:目安は40%以上が理想、30%未満は要注意)
-
企業の総資本に対して自己資本(株主資本や剰余金など返済不要の資本)がどの程度の割合を占めているかを表す財務指標です。企業の財務の健全性や安定性を測る重要な指標とされています。 自己資本比率が高いほど、経営は安定し倒産リスクが低いと評価されます。
- 流動比率:(流動資産÷流動負債×100:目安は200%以上が理想、100%未満は危険)
-
企業の短期的な支払能力や財務安全性を示す代表的な指標です。企業が1年以内に現金化できる資産(流動資産)で、1年以内に支払わなければならない負債(流動負債)をどの程度カバーできるかを表しています。
- ROE :(当期純利益÷自己資本:目安は8%以上、伊藤レポートが発表されてから一つの目安となった)
-
企業が株主から預かった資本(自己資本)を使って、どれだけ効率的に利益を生み出しているかを示す指標です。 日本の企業だと8-10%ぐらいが多いです。アメリカの企業では14-18%と日本企業の2倍近い数値になっています。 株式投資のリターンの目安が5%前後と言われているので、非常に高いことがわかりますね。デメリットとして自己資本を減らすとROEは向上します。それだと本末転倒になりかねませんね。そこで活躍するのがデュポンシステムです。
- デュポンシステム
-
ROEを「3つの要素」に分解して、企業のどこに強みや課題があるかをより詳細に分析できる手法です。
①売上高純利益率=当期純利益 ÷ 売上高:売上高に対してどれだけ純利益を上げたか
②総資産回転率=売上高 ÷ 総資産:企業が保有する資産をどれだけ効率的に使って売上を上げたか
③財務レバレッジ=総資産 ÷ 自己資本:資産のうち自己資本が占める割合
3つの式の中にある分母・分子を消していくと、最終的には当期純利益÷自己資本だけが残ります。つまりはROEの式と同じですね。
高いほど他人資本(借入など)を活用(安全性) それぞれはトレードオフの関係にあるため、上げることは非常に難しいと言われています。
資産=良いものとは限らない!?
資産って聞くといいイメージがありますよね。実際に資産って「将来に収益をもたらす可能性のあるもの」なので基本的にはたくさんあった方がいいです。しかしそれは本当に資産性があればですが…
例えば、、、
棚卸資産(在庫)が異常なほど膨れ上がってる!!
このように在庫が多すぎると:
- 売れ残りで倉庫代がかかる
- 古くなって価値が下がる(評価減)
- 何よりキャッシュフローを圧迫する
例えば、アパレル企業で去年の服が大量に残っていたら…想像するだけでゾッとしますよね。このように一見すると良いものでも分析結果ではよくないこともあります。過去からの傾向、業界の平均値などと比較すると良し悪しが見えてきます。
負債=悪ではない!「借金」と「株式」の賢い使い分け
この企業は借入がない!優秀な会社だね!
すごいね!無借金経営ってやつだ!!
「無借金経営」ってたまに聞きますよね。良さそうに聞こえますが、本当にそうでしょうか?
- 利息:年1〜3%程度
- 税効果で実質コストは30〜40%減(いわゆる税効果ですね)
- 実質コスト:0.6〜2%程度
それでは次に株式発行(資産の部)の場合を見てみましょう!
- 配当金:3〜5%
- 株主優待コスト
- 株主総会・監査費用
- トータルコスト:10%前後 *もっと低くなる場合もあります
実は借入金の方がコストは低く抑えられます!
ちょっと考えると、株式発行で得たお金は返済義務がありません。そのため、投資家の方がリスクを負うため要求も高くなりますよね。
逆に急いで借入金を返済する場合もあります。それはなぜでしょうか?おそらくその企業は自己資本比率を上げて、いつか大きな借入をする際にスムーズに資金調達ができるように準備をしている可能性もあります。
企業にとっての最適化を理解することが大切
大切なのは「その企業にとって何がベストか」を考えること。
- IT企業なら借入は少ない傾向がある(設備投資が少ない)
- 製造業なら適度な借入はむしろ健全(設備投資が必要)
- 小売業なら買掛金を上手く使うのが大事
このように業界の特性を理解することが、真の分析への第一歩です。いろんな業界のビジネスモデルに興味を持って調べてみましょう!
深掘り質問!プロの目線で深く知る!
これまでもすでに生成AIの凄さはお気づきのはず!
でも実は本番はここからです!有価証券報告書を読み込ませ、企業分析をするプロンプトを打ち込んだのでこのチャットルームではすでに企業分析のプロフェッショナルになったAIがいるのです。
企業によって大切なポイントは違いますし、業界によっても傾向は大きく異なります!なので追加質問をして、深く理解していきましょう!
資産の部を深掘り!
キャッシュポジション
「現預金の水準は業界平均・傾向と比較して適切ですか?月商の何ヶ月分ありますか?」
” Cash is King” という言葉がある通り、やはり資産の王様は現金です。また会社は利益が出なくても潰れませんが、現金がなくなると潰れます。キャッシュポジションはとても大切です。
キャッシュについては下の記事で深くご紹介していますのでこちらも見てみてくださいね。
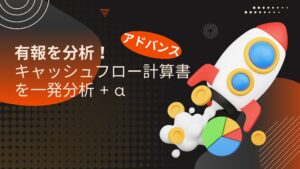
固定資産の減損リスク
「固定資産に減損の兆候はありますか?特に注意すべき資産はありますか?」
「資産は将来において利益をもたらすもの」です。言い換えると将来、利益をもたさなければ資産とは言えなくなります。会社の状況が大きく変わったり、固定資産が利益をもたらさなくなるようは場合は価値を下げなければなりません。とても悲しくなるし、損失は大きくなりがちです。このように資産が大きいから良いというわけではないし、潜伏している負債があることも…
回収可能性の検討
「売掛金や貸付金について、回収リスクはありますか?貸倒引当金の計上は適切ですか?
売掛金・貸付金などは大切な資産ですが、本当に現金で回収できなければ意味がありません。「企業が回収できないなんてあるの?」と思いますよね?でも実際にあるんです!しかも企業はあらかじめ貸し倒れることを見積もって、減らしているんですよ。それが妥当かも確認してみましょう!
負債の部を深掘り!
財務制限条項(コベナンツ)の有無
「借入金に財務制限条項はついていますか?もしあれば、抵触リスクはどの程度ですか?」
借入をするときに、銀行と約束をすることがあります。例えば「売上高はいくら以上を出してくださいね」や、「資本比率はいくら以下にはしないでくださいね」など財務指標の目標値を設定されます。もしそれを下回ると、すぐに全額返済しなければならなくなります。またそれは会社の存続の危機に直面しているということも言えます…
もし業績が下火な企業だと確認した方がいいかもしれませんね。
潜在的なリスクを深掘り
最後に、今はなんともなくても将来的に大きなマイナスになる可能性のあるものを探ってみましょう。どんな企業でもあるというものではありませんが、もし発生したら企業の財務状況に大きな影響を与えるものもあります。
リスク = 発生確率 × 影響度
偶発債務の有無
「保証債務や訴訟など、将来負債になりそうなものはありますか?」
会計のテクニカルワードでは偶発事象、偶発債務と言われるものです。今は損失を計上しなくてもいいけど、ある条件を満たしたらマイナスになるような潜伏中のリスクですね。例えば、係争中の訴訟、債務保証、先物取引などがあります。
繰延税金資産の回収可能性
「繰延税金資産は本当に回収できそうですか?将来の課税所得は十分見込めますか?」
実は、毎年企業が計上している税金って支払った税金だけじゃないんです!
大きく分けると2つに分けることができます。
- 利益が出た時に支払う法人税
- 将来払うかもしれない繰延税金資産・負債
そして困ったこと(?)に②の繰延税金資産・負債の方が影響が大きいのです!さらにこの話をややこしくするのが、繰延税金資産・負債は企業が見積りを出した額であるということです。この話はとても複雑になるので一旦ここでやめときます!(気になった方は生成AIに聞いてみてくださいね)
つまり結論は、生成AIに企業が見積もった資産・負債は問題なさそうか聞いてみようというものです!
実践例:売掛金分析の深掘り
3期比較した際の売掛金分析について、具体例を見てみましょう。
基本的には売上が増えると、売掛金も増えます。でも両方の伸び率に着目してみましょう!
- 売上高の伸び率:10%
- 売掛金の伸び率:30%
この差は何を意味するか?回収が遅れている可能性大です!
こうなると売掛金の回収可能性が怪しいですね。
まとめ
いかがでしたか?生成AIを使えば、難しそうな貸借対照表分析も、意外と簡単にできるんです。
ポイント:
- まずは基本プロンプトで全体像を把握
- 気になる点は追加質問で深掘り
- 数字の裏にある「意味」を考える
生成AIを活用した有報分析の一番の強みは、プロンプトで分析をした後の深掘り質問にあります。実際に自分自身でも有価証券報告書を見ながら質問をどんどんやってみましょう!
AI相手なので恥ずかしい質問はありません。基本的な用語でも構いません!
とにかく質問して知見・視野を広げていきましょう!



コメント